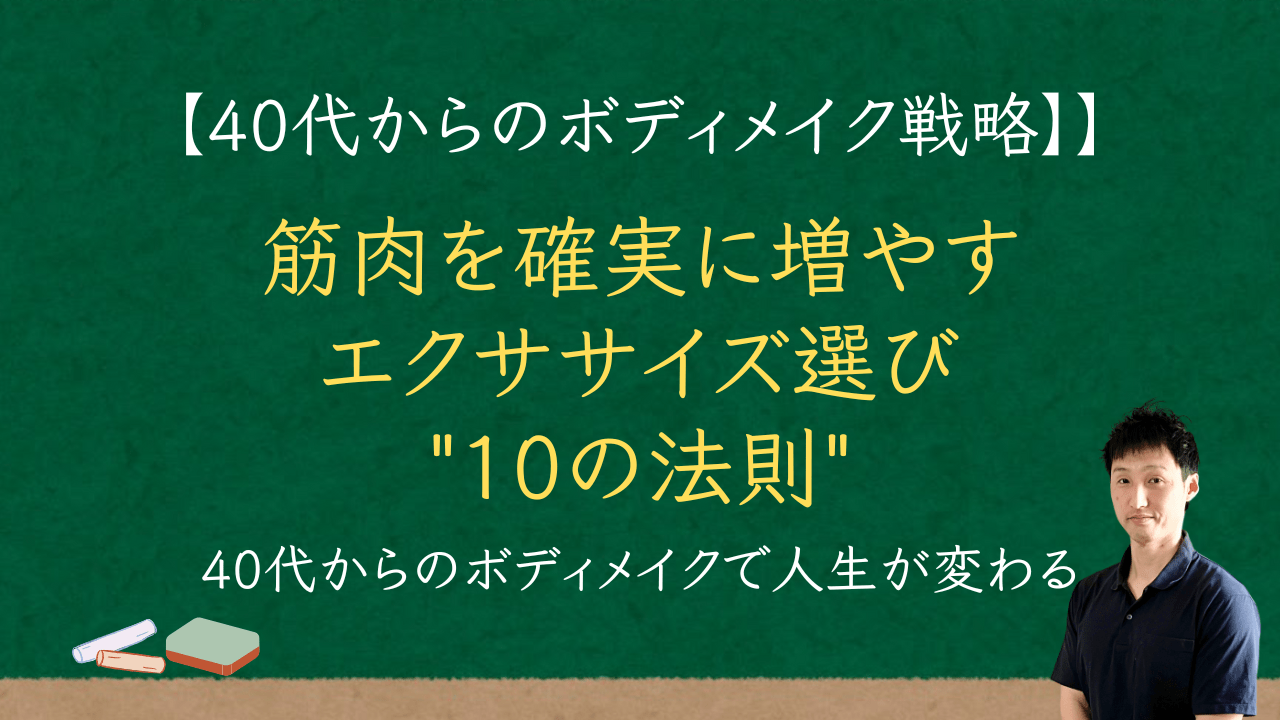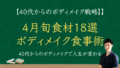【40代からの筋トレ革命】失敗しない!筋肉を確実に増やすエクササイズ選び”10の法則”|正しい知識で理想のボディへ
「40代を過ぎて体型が気になり始めた」「健康診断の数値も気になるし、そろそろ運動しないと…」そう思って筋トレに関する情報を集めても、あまりにも多くの情報が溢れていて、結局どれが本当に自分にとって効果的なのか分からなくなっていませんか?
「楽して痩せる!」「飲むだけで筋肉がつく!」といった魅力的な宣伝文句に惹かれつつも、心のどこかで「そんなうまい話はないよな…」と感じている方も多いのではないでしょうか。特に40代以降の体は、若い頃と同じような無理なトレーニングや、根拠の薄い情報に振り回されると、効果が出ないばかりか、怪我のリスクを高めてしまう可能性もあります。
ご安心ください。この記事では、巷に溢れる玉石混交の情報に惑わされず、科学的な根拠に基づいた「本当に効果的な筋トレエクササイズの選び方」を、10個の明確な基準としてご紹介します。これは、フィットネス科学の専門家であるDr. Mike Israetelが提唱する方法をベースに、40代以降の皆さんが実践しやすいように分かりやすく解説したものです。
なぜこの10の基準が有効なのでしょうか? それは、これらの基準が筋肉が成長する生理学的なメカニズムに基づいているからです。小手先のテクニックではなく、筋肉が大きくなる原理原則に沿ったエクササイズを選ぶことで、回り道せず、着実にあなたのボディメイクを成功へと導きます。
この記事を読むことで、あなたは以下のことを理解できるようになります。
-
無数にある筋トレエクササイズの中から、自分にとって本当に効果的な種目を見極める具体的な方法
-
なぜそのエクササイズが効果的なのか、その科学的な理由
-
時間と労力を無駄にしない、効率的なトレーニングの実践
-
怪我のリスクを減らし、安全に長く続けられるトレーニングの知識
もう情報に振り回されるのは終わりにしましょう。この記事を読めば、あなたは自信を持ってエクササイズを選び、40代からでも理想の体を作るための、確かな一歩を踏み出すことができるようになります。
※こちらの記事は下記の動画を参考に作成しております。
筋肉を育てるエクササイズ選び、10のチェックポイント
それでは早速、効果的なエクササイズを見極めるための10の基準を見ていきましょう。これらの基準を総合的に満たすエクササイズほど、あなたの筋肉を効率よく成長させてくれる可能性が高いと言えます。
法則1:筋肉を深く「ストレッチ」できるか?
まず最初の基準は、エクササイズ動作の中で、ターゲットとなる筋肉をしっかりと伸ばせる(ストレッチできる)かどうかです。
なぜストレッチが重要なのでしょうか? それは、筋肉が伸ばされた状態で力を発揮する(張力がかかる)時に、筋肥大のシグナルがより強く送られることが研究で示唆されているからです。筋肉は、引き伸ばされながら負荷に耐えるという状況(伸張性収縮、エキセントリック収縮とも呼ばれます)で、より大きな刺激を受けやすいのです。
例えば、チェストプレス(胸のトレーニング)を行うマシンを想像してみてください。あるマシンでは、バーを胸に近づけても、まだもう少し深く下ろせそうなのに、マシンの構造上そこで止まってしまうとします。これでは、大胸筋を十分にストレッチすることができません。一方で、別のマシンやダンベルプレスなら、もっと深く下ろして大胸筋をしっかりストレッチできるかもしれません。この場合、後者の方が筋肥大にとってはより有利なエクササイズと言える可能性があります。
もちろん、全てのエクササイズで最大限のストレッチが必要なわけではありません。しかし、他の条件が同じくらいであれば、より深く筋肉をストレッチできるエクササイズを選ぶ方が、筋肥大の効果、さらには関節の可動域や柔軟性の向上にも繋がり、より機能的な体を作る上で有利になります。
【ポイント】
エクササイズを選ぶ際、「この動きで、ターゲットの筋肉はしっかり伸びているかな?」と意識してみましょう。
法則2:深いストレッチの位置で「高い負荷」がかかるか?
2番目の基準は、法則1と密接に関連しています。それは、筋肉が最もストレッチされたポジションで、しっかりと負荷(張力)がかかっているかということです。単にストレッチされるだけでなく、その伸びた状態で強い力を発揮する必要があることが重要です。
少し専門的になりますが、エクササイズによっては、筋肉が最も伸びているポジションで負荷が抜けやすいものがあります。典型的な例が、立った状態で行う「スタンディング・ダンベルカール」(力こぶ、上腕二頭筋のエクササイズ)です。
腕を完全に下ろしたポジションでは、上腕二頭筋は比較的ストレッチされています。しかし、重力は真下にしかかからないため、この一番下のポジションでは、ダンベルの重さは主に腕の骨や腱、靭帯で支えられ、上腕二頭筋にはほとんど負荷がかかっていません。動作を開始して腕を少し曲げ始めても、負荷はまだ小さいままです。負荷が最大になるのは、肘が90度くらいに曲がった中間地点であり、そこからさらに巻き上げると、また負荷は小さくなっていきます。
つまり、スタンディング・ダンベルカールは、筋肉が最もストレッチされるポジションでの負荷が小さいエクササイズと言えます。
これに対して、「インクライン・ダンベルカール」はどうでしょうか? ベンチに角度をつけてもたれかかり、腕を体の後ろに垂らした状態からカールを行います。この開始姿勢では、肩関節の伸展も加わるため、上腕二頭筋はより強くストレッチされます。そして、この深くストレッチされたポジションでも、ダンベルの重さ(重力)は上腕二頭筋に対してしっかりと負荷をかけ続けます。
【ポイント】
エクササイズ中に、「一番きついのはどのポジションかな?」「筋肉が一番伸びているところで、しっかり負荷を感じるかな?」と考えてみましょう。ストレッチポジションで負荷が最大になるエクササイズは、特に効果が高い可能性があります。
法則3:「5~30回」の反復で限界近くまで追い込めるか?
3番目の基準は、使用する重量が適切で、1セットあたり5回から30回の反復で、あと数回しかできないという限界に近い状態まで追い込めるかどうかです。
軽いのダンベルを持って、何十回も繰り返すようなエクササイズを見たことはありませんか? もしその重さで60回も70回もできてしまうとしたら、それは筋肉を成長させるための刺激としては軽すぎる可能性が高いです。
筋肥大を引き起こすためには、筋肉に対して「今のままではこの負荷に対応できない、もっと強くならなければ!」と思わせるような、十分に挑戦的な負荷を与える必要があります。研究では、1セットあたり5回程度の低回数から、30回程度の中~高回数まで、限界に近い努力度で行えば、同程度の筋肥大効果が得られることが示されています。
重要なのは、「限界に近い努力度」であることです。例えば、10回で限界が来る重量(10RM)を使って10回行うのはもちろん、15回で限界が来る重量を使って12~13回行う(限界まであと2~3回残す)といった形でも効果的です。
自重トレーニング、例えば腕立て伏せ(プッシュアップ)はどうでしょうか? もしあなたが35回以上楽にできてしまうなら、通常の腕立て伏せは、あなたにとって筋肥大にはやや物足りない刺激になっているかもしれません。
【自重トレーニングなどを適切な負荷にする工夫】
-
負荷を追加する: 加重ベストを着る、背中にプレートを乗せる(補助者が必要)、ゴムバンドを使うなど。
-
動作を難しくする:
-
デフィシット・プッシュアップ: 手を台などの上に置いて、より深く体を下ろすことで、大胸筋のストレッチを深め、負荷を高めます。
-
動作スピードを調整する: 特に下ろす動作(エキセントリック)をゆっくり(3~4秒かけて)行う。
-
可動域を限定する(パーシャルレップ): 例えばスクワットで、一番下から2/3~3/4程度までしか上がらず、筋肉が休まるトップポジションを避けることで、筋肉への負荷を維持します。これはディップスやプッシュダウンなど多くの種目に応用できます。
-
-
トレーニングの後半に行う: 他のウェイトトレーニングで筋肉が疲労した後に自重トレーニングを行うことで、軽い負荷でも限界に達しやすくなります。例えば、ベンチプレスやダンベルプレスの後に腕立て伏せを行うなど。
【ポイント】
選んだエクササイズで、1セットあたり5~30回の範囲で「きつい!」と感じられる重量設定になっていますか? 楽にこなせる回数が30回を大幅に超える場合は、負荷を高める工夫をしましょう。
法則4:継続的に「負荷(重量や回数)を増やして」いけるか?
4番目の基準は、そのエクササイズで、長期的に負荷を増やしていくことができるかどうか、つまり漸進性過負荷の原則を適用できるか、ということです。
筋肉が成長し続けるためには、常に少しずつ負荷を高めていく必要があります。体が慣れてしまった負荷では、それ以上の成長は望めません。「前回よりも少し重い重量を上げる」「前回と同じ重量で、1回でも多く反復する」といった進歩が重要になります。
バーベルやダンベル、多くのマシンエクササイズは、プレートを付け替えたり、ピンの位置を変えたりすることで、少しずつ重量を増やしていくことが容易です。これが、これらの器具が筋トレの王道とされる理由の一つです。
一方で、例えばメディシンボール投げのようなエクササイズは、爆発的なパワー養成には有効ですが、段階的に重さを増やしていくのが難しい場合があります(様々な重さのボールがあれば別ですが)。
自宅トレーニングなどで、決まった重さのダンベルしかない場合はどうでしょうか? 例えば20kgのダンベルしかない場合、すぐに21kgにするのは難しいですよね。しかし、諦める必要はありません。反復回数を増やしていくことでも、漸進性過負荷は達成できます。
-
今週:20kgで10回 x 3セット
-
来週:20kgで11回 x 3セット
-
再来週:20kgで12回 x 3セット
このように、毎週1回ずつでも反復回数を増やしていくことで、筋肉への刺激を高めることができます。ただし、前述の通り、回数が30回を大幅に超えてくると筋肥大の効果が頭打ちになる可能性があるので、可能であればどこかのタイミングでより重い重量に移行するか、負荷を高める他の工夫(法則3参照)を取り入れるのが理想的です。
【ポイント】
選んだエクササイズは、重量や回数を少しずつ増やしていく計画が立てやすいですか? 進歩を記録し、常に少し上のレベルを目指せるエクササイズを選びましょう。
法則5:ターゲットの筋肉に集中できる「安定性」があるか?
5番目の基準は、エクササイズを行う際に、体が十分に安定しているかどうかです。不安定な状態でのトレーニングは、ターゲットとする筋肉の力を最大限に引き出すことを妨げてしまう可能性があります。
バランスボールの上に乗ってスクワットをしたり、グラグラするベンチでダンベルプレスをしたりするような「不安定トレーニング」を見たことがあるかもしれません。一見、体幹も鍛えられて高度なトレーニングのように思えますが、筋肥大を主な目的とする場合、これは逆効果になることが多いのです。
なぜなら、体が不安定な状態だと、筋肉は最大の力を発揮するよりも、バランスを取ることを優先してしまうからです。転倒しないように、脳が筋肉の出力にブレーキをかけてしまうのです。その結果、ターゲットとする筋肉(例えばスクワットなら大腿四頭筋や大臀筋)は、本来発揮できるはずの力の何割かしか使われず、筋肥大に必要な強い刺激が入りにくくなります。研究によっては、不安定な状態では安定した状態に比べて筋活動が30~50%も低下することが示されています。
特に、筋肉の中でも大きくてパワーがあり、筋肥大のポテンシャルが高い「速筋線維」は、高い負荷がかかったり、他の筋線維が疲労したりして、「いよいよ出番だ!」という状況にならないと活動しません。不安定なトレーニングでは、この速筋線維が十分に動員されないまま終わってしまう可能性が高いのです。
「でも、不安定なトレーニングは体幹(スタビライザー)が鍛えられるのでは?」という意見もあります。しかし、そもそも「スタビライザー」という特定の筋肉群が存在するわけではありません。多くの筋肉は、動作に応じて体を安定させる役割も担っています。そして、安定させるための筋活動は、必ずしも筋肥大を引き起こすほどの強い刺激ではありません。お皿を運ぶときに前腕の筋肉が使われるのと同じで、使われてはいますが、それが前腕を太くするためのトレーニングになるとは言えませんよね。
筋肥大を効率的に進めたいのであれば、ダンベル、バーベル、マシンなど、安定した土台の上で行えるエクササイズを選び、ターゲットの筋肉にしっかりと集中して力を発揮できる環境を作りましょう。
【ポイント】
そのエクササイズは、バランスを取ることに必死になっていませんか? ターゲットの筋肉に意識を集中し、しっかりと力を込めることができる、安定したエクササイズを選びましょう。
法則6:関節にとって「快適」で、痛みがないか?
6番目の基準は、エクササイズがあなたの関節にとって、できるだけ快適に感じられるかどうかです。
高重量を扱う筋力トレーニングですから、多少のきつさや筋肉の疲労感は当然伴います。しかし、関節そのものに痛みや強い違和感がある場合は注意が必要です。
特定のマシンを使うと、どうも肩や肘、膝が痛む…という経験はありませんか? 人間の骨格や関節の形状は一人ひとり微妙に異なるため、ある人にとっては非常にやりやすいマシンでも、別の人にとっては関節に負担がかかる角度になってしまうことがあります。
【良いサインと悪いサイン】
-
良いサイン:
-
ウォーミングアップの段階で、関節にスムーズさを感じる。
-
最初は少し違和感があっても、ウォーミングアップを進めるうち、または数週間続けるうちに関節が慣れてきて快適になる。
-
セット中、セット間、トレーニング翌日などに関節の痛みが増悪しない。
-
4~6週間継続しても、関節に痛みが出ない、むしろ調子が良い。
-
-
悪いサイン:
-
ウォーミングアップの段階から、特定の関節に「嫌な感じ」や痛みがある。
-
セットを重ねるごと、またはトレーニングを続けるごとに関節の痛みが増してくる。
-
トレーニング数日後も関節の痛みが続く。
-
もし特定のエクササイズで常に関節が痛むのであれば、それはあなたにとって良いエクササイズとは言えません。無理して続けると、慢性的な痛みや怪我につながり、トレーニング自体ができなくなってしまう可能性があります。
幸い、ほとんどの筋肉には、様々な代替エクササイズが存在します。あるチェストプレスマシンで肩が痛むなら、別のマシン、ダンベルプレス、インクラインプレス、ディップスなどを試してみましょう。自分にとって関節が快適で、かつ筋肉にしっかり効かせられるエクササイズを見つけることが、長く安全にトレーニングを続けるための鍵となります。特に40代以降は、関節への配慮がより重要になります。
【ポイント】
そのエクササイズ、関節は悲鳴を上げていませんか? 筋肉の疲労感と関節の痛みを区別し、関節に優しいエクササイズを選びましょう。痛みがある場合は、フォームを見直すか、別の種目に変える勇気も必要です。
法則7:ターゲットの筋肉が「しっかり使われている感覚」があるか?
7番目の基準は、そのエクササイズが、狙っている筋肉をしっかりと刺激している、という主観的な感覚があるかどうかです。これはいくつかの要素から判断できます。
-
筋肉の「張り(テンション)」を感じるか?
エクササイズ中、特に筋肉が伸ばされながら力を入れている局面(エキセントリック局面)で、ターゲットの筋肉がパンパンに張っているような感覚、時には引きちぎられそうな強いストレッチ感を感じられるでしょうか? 例えば、スティッフレッグドデッドリフトやルーマニアンデッドリフトを行う際の、ハムストリングス(太もも裏)の強烈な張りは、その典型例です。この感覚が強いエクササイズは、効果的な刺激が入っている可能性が高いです。 -
高回数で「バーン(燃焼感)」を感じるか?
15回以上の比較的高回数でセットを行った際に、ターゲットの筋肉が熱くなるような、焼けるような感覚(バーン)が出てくるでしょうか? 例えば、ランジを行う際に、フォームによって効く場所が変わってきます。膝がつま先より大きく前に出るような短い歩幅だと太もも前(大腿四頭筋)にバーンを感じやすく、お尻を後ろに引くように深くしゃがみこむような長い歩幅だとお尻(大臀筋)にバーンを感じやすくなります。もしお尻を狙っているのに太ももばかりが熱くなるなら、フォームを見直すか、別の種目を検討する必要があるかもしれません。狙った場所にバーンを感じられるのは、その筋肉がしっかり活動している良い兆候です。 -
セット後に「筋肉の弱りや震え」を感じるか?
エクササイズのセットが終わった直後、ターゲットとした筋肉に力が入らなくなり、プルプルと震えるような感覚はありますか? 例えば、レッグエクステンションを限界まで追い込んだ後に、立ち上がろうとすると膝がガクガクするような感覚です。これは、筋肉が一時的に疲労困憊している証拠であり、強い刺激が入ったサインと言えます。 -
トレーニング中に「パンプ」を感じるか?
トレーニング中または直後に、ターゲットの筋肉が血液で満たされ、パンパンに張っているような感覚(パンプ)はありますか? アーノルド・シュワルツェネッガーが「パンプは最高の感覚だ」と言ったのは有名ですが、このパンプ感と筋肥大の間には関連がある可能性が研究でも示唆されています。強いパンプが得られるエクササイズは、血流を増加させ、筋肉に栄養を送り届け、成長を促す環境を作っている可能性があります。 -
トレーニング後に「筋肉痛」が来るか?
トレーニングの数時間後、または翌日以降に、ターゲットとした筋肉に心地よい(あるいは強烈な)筋肉痛(遅発性筋肉痛、DOMS)は来ますか? 筋肉痛が必ずしも筋肥大の必須条件ではありませんが、特に新しいエクササイズや強い刺激を与えた後には起こりやすい現象です。狙った筋肉に適切な筋肉痛が来ることは、その筋肉がしっかりと破壊され、回復・成長のプロセスに入った可能性を示す一つの指標となります。ただし、日常生活に支障が出るほどの激しい筋肉痛は、オーバートレーニングのサインかもしれないので注意が必要です。
これらの感覚は主観的なものであり、絶対的な指標ではありません。感覚がなくても筋肉が成長することもあります。しかし、これらの感覚(張り、バーン、疲労感、パンプ、筋肉痛)を狙った筋肉でしっかりと感じられるエクササイズは、そうでないエクササイズに比べて、あなたにとって効果的である可能性が高いと言えるでしょう。これはマインドマッスルコネクション(筋肉と意識の繋がり)とも呼ばれ、トレーニング効果を高める上で重要な要素です。
【ポイント】
トレーニング中に、「今、どこの筋肉を使っているかな?」「狙った筋肉に効いている感覚はあるかな?」と意識を向けてみましょう。上記の感覚が得られるエクササイズは、あなたとの相性が良い可能性があります。
法則8:全身の疲労に見合うだけの「筋肉への刺激」があるか?
8番目の基準は、そのエクササイズが生み出す全身的な疲労に対して、見合うだけのターゲット筋肉への刺激が得られているか、というコストパフォーマンスの視点です。
スクワット、デッドリフト、ベントオーバーロウといった、多くの関節と筋肉を同時に使う「コンパウンド種目(多関節種目)」は、非常に効果的な反面、全身的な疲労も大きくなりやすいエクササイズです。具体的には、以下のような疲労が考えられます。
-
体幹・脊柱への疲労: 高重量を支えることによる背骨周りの筋肉の疲労。
-
精神的な疲労: 高重量への挑戦や限界までの追い込みによる精神的な消耗。「よし、やるぞ!」という気合が必要。
-
心血管系の疲: 息が上がり、心拍数が急上昇するような、循環器系への負担。高回数のスクワットなどは特に顕著。
これらの全身的な疲労が大きいこと自体は、必ずしも悪いことではありません。問題は、その大きな疲労(コスト)に見合うだけの、ターゲット筋肉への十分な刺激(リターン)が得られているかどうかです。
例えば、スティッフレッグドデッドリフトは、体幹への負荷も大きく精神的にもきついエクササイズですが、ハムストリングスと大臀筋に対して非常に強烈なストレッチと負荷を与えることができるため、「コストは高いがリターンも大きい」優れたエクササイズと言えます。ランジも全身運動に近く、心肺機能も精神力も要求されますが、正しく行えば大臀筋と大腿四頭筋に素晴らしい刺激を与えられます。
一方で、もしあるエクササイズが、全身をとてつもなく疲労させる割には、ターゲットとしている筋肉への「効いている感覚」(張り、バーン、パンプ、筋肉痛など)があまり得られないとしたら、それはあなたにとってコストパフォーマンスの悪いエクササイズかもしれません。
理想的なエクササイズは、全身的な疲労は最小限に抑えつつ、ターゲット筋肉への局所的な刺激を最大化できるものです。マシンエクササイズや、単一の関節だけを動かす「アイソレーション種目(単関節種目)」の中には、このような特徴を持つものも多くあります。
【ポイント】
そのエクササイズは、あなたをヘトヘトに疲れさせるだけで、肝心の筋肉にはあまり効いていない、なんてことはありませんか? 全身的な疲労度と、ターゲット筋肉への刺激のバランスを考えてみましょう。疲労が大きいエクササイズを選ぶなら、それ相応の筋肉への効果を実感できるものを選びたいですね。
法則9:やっていて「楽しい」「好きだ」と感じられるか?
9番目の基準は、非常にシンプルですが、実はとても重要な要素です。それは、あなたがそのエクササイズを好きで、やっていて楽しいと感じ、継続的に取り組みたいと思えるかどうかです。
なぜ「楽しさ」や「好み」が重要なのでしょうか? それは、継続こそがボディメイク成功の最大の鍵だからです。どんなに理論上優れたエクササイズでも、嫌々やっていたり、苦痛でしかなかったりすれば、長続きさせるのは困難です。
私たちは、目標達成のために「モチベーション」を頼りに頑張ることがあります。「理想の体になるために、このきついトレーニングを乗り越えよう!」という感じです。これは素晴らしいことですが、モチベーションは日によって波があったり、目標が遠く感じられると薄れてしまったりすることもあります。
しかし、もしトレーニング自体が楽しかったらどうでしょうか? 友達と遊んだり、趣味に没頭したりするのにモチベーションが必要ないのと同じように、トレーニングが「やりたいこと」になれば、モチベーションに頼らずとも自然とジムに向かい、継続することができるようになります。
「好きこそ物の上手なれ」と言いますが、筋トレも同じです。好きなエクササイズなら、
-
自然と集中力が高まり、フォームも丁寧になる
-
セット間の休憩も惜しんで次に取り組みたくなる
-
「もっと上手くなりたい」「もっと重量を伸ばしたい」という意欲が湧く
-
結果として、トレーニング効果も高まりやすい
もちろん、効果を出すためにはある程度の努力や不快感を乗り越える必要はあります。楽なだけのトレーニングでは筋肉は成長しません。しかし、同じような効果が期待できるエクササイズが複数あるのであれば、その中であなたが最も「やってみたい!」「これなら続けられそう!」と感じるものを選ぶことは、長期的な成功のために非常に賢明な戦略です。
例えば、次のトレーニングメニューを組む際に、同じ部位を鍛える候補のエクササイズが3つあったとします。どれも理論的には良さそうだけど、どれにしようか迷ったら、「一番ワクワクするのはどれか?」「一番新鮮で、試してみたいのはどれか?」「これで記録を伸ばしてみたい!と思えるのはどれか?」と自問自答してみてください。その答えが、あなたにとって現時点で「最高の」エクササイズである可能性が高いのです。
【ポイント】
筋トレは修行ではありません。もちろん努力は必要ですが、その中に楽しさを見つけることが継続の秘訣です。色々なエクササイズを試してみて、「これは好き!」「これはしっくりくる!」という種目を見つけましょう。
法則10:上記に反するエクササイズは避ける
最後の法則は、これまでの9つの法則の裏返しです。つまり、これまでの基準に照らして、明らかにマイナス面が多いエクササイズは避けるべき、ということです。
-
筋肉を十分にストレッチできない
-
ストレッチポジションで負荷が抜けてしまう
-
適切な負荷(5-30回)で追い込めない
-
負荷を漸進的に増やしていくのが難しい
-
不安定で筋肉に集中できない、怪我のリスクが高い
-
常に関節に痛みを感じる
-
狙った筋肉に効いている感覚が全くない
-
全身はやたら疲れるのに、筋肉への刺激が少ない
-
やっていて苦痛でしかない、全く好きになれない
もしあなたが選ぼうとしている、あるいは現在行っているエクササイズが、これらのネガティブな特徴を複数持っているとしたら、それは時間と労力の無駄になっている可能性があります。勇気を持って、そのエクササイズをメニューから外し、より効果的な代替種目を探すことを検討しましょう。
まとめ:賢いエクササイズ選びで、40代からのボディメイクを成功へ
今回は、40代以降の私たちが、情報に惑わされずに本当に効果的な筋トレエクササイズを選ぶための「10の法則」をご紹介しました。
【効果的なエクササイズ選び・10の法則 チェックリスト】
-
□ 筋肉を深くストレッチできるか?
-
□ 深いストレッチの位置で高い負荷がかかるか?
-
□ 5~30回の反復で限界近くまで追い込めるか?
-
□ 継続的に負荷(重量や回数)を増やしていけるか?
-
□ ターゲットの筋肉に集中できる安定性があるか?
-
□ 関節にとって快適で、痛みがないか?
-
□ ターゲットの筋肉がしっかり使われている感覚(張り・バーン・疲労感・パンプ・筋肉痛)があるか?
-
□ 全身の疲労に見合うだけの筋肉への刺激があるか?
-
□ やっていて楽しい・好きだと感じられるか?
-
□ 上記に反する明らかなマイナス面がないか?
全てのエクササイズがこれらの基準を完璧に満たすわけではありません。しかし、より多くの基準を満たすエクササイズを、あなたのトレーニングの中心に据えることで、より安全かつ効率的に筋肉を成長させ、理想のボディメイクを達成することができるはずです。
特に40代からは、体力や回復力、関節の状態なども考慮しながら、無理なく続けられる、自分に合った方法を見つけることが重要です。これらの法則は、そのための道しるべとなるでしょう。
今日から、あなたのトレーニングメニューを見直す際に、ぜひこの10の法則を参考にしてみてください。一つ一つのエクササイズを吟味し、より質の高いトレーニングを実践することで、あなたの体はきっと応えてくれるはずです。
お知らせ
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
▶ 一人ひとりに合わせた、最適なボディメイクプランを知りたい方へ
オンラインでのパーソナルトレーニング指導も行っています。あなたの目標やライフスタイルに合わせた、効果的なプログラムをご提案します。興味のある方は、お気軽にご相談ください。
https://coconala.com/users/3522116
一緒に、理想の体を目指して頑張りましょう!